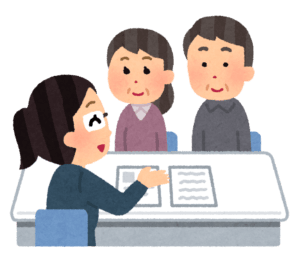☆気分障害(うつ病)での障害年金のもらい方
こんにちは!
障害年金に特化した美帆社会保険労務士事務所の小池美帆です。
今回は障害年金の対象となる精神の障害のうち、気分障害(うつ病)について解説します。
まずはじめに、年金の認定基準で精神の障害は以下のように区分されています。
「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」←ブログ![]() ☆統合失調症について解説します!
☆統合失調症について解説します!
「気分(感情)障害」
「症状性を含む器質性精神障害」
「てんかん」
「知的障害」
「発達障害」
気分(感情)障害には長期にわたって気持ちが塞ぎ込む「うつ病」と、うつ状態と躁状態(気分が高揚した状態がつづく)を繰り返す「双極性障害」、調子のよい時期を数日から数週間もちその他ほとんどの期間疲れや抑うつを感じる「気分変調症」などがあります。
うつなどの気分障害はある程度その状態が続くと診断されますが、障害年金は初診日から1年6か月経過した日か、障害が治った(症状が固定した)場合はその日となるため、定期的に受診して日々の状態を主治医へ的確に伝えることが大切になります。
初診日は精神科で初めてうつ病と診断された日とは限りません。
うつ病は前駆症状として睡眠障害、身体の痛み、食欲や体重の異変などの身体症状があらわれる方がいます。のちにその症状がうつ病の前駆症状として分かれば、その症状で初めて病院にかかった日が初診日となります。
1.気分障害の障害認定基準とは?
障害認定基準で気分(感情)障害の程度は以下の通りです。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 精神の 障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 2級 | 精神の 障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
| 3級 | ①精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ②精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
| 障害手当金 | 精神に 、労働が 制限を 受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療及びその症状の経過、具体的な日常生活状況などにより総合的に認定されます。
主に活動の範囲がベッド周辺に限られ、他人の介助がなければ日常生活のほとんどができないほどの障害の状態が1級相当です。
活動の範囲が家の中に限られ、家庭内の軽作業はできるが日常生活に著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加える日必要があるほどの障害の状態が2級に相当します。
3級は労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とする状態です。
また、初診日から5年以内に病気やけがが治り、3級よりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)に該当します。
2.等級に該当する障害の程度とは?
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のようになります。
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり又はひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの |
『気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。』とされています。
障害の程度は認定基準日時点での診断書に記載された障害の程度だけで判断されるのではなく、それまでの経過や日常生活の状態を考慮して認定されるということです。
3.うつ病(気分障害)での障害年金のもらい方は?
障害年金を受給するための大前提として、国民年金の納付要件を満たしている必要があります。この納付要件をクリアしていなければ、現在の障害がどんなに重いものであっても障害年金を受給することはできないとても重要な要件です。
納付要件が満たされていれば、次に初診日と障害認定日を確認します。
上述した通り、初診日は例えばうつ病と最初に診断が出された病院とは限りません。その障害と関係する症状で初めて病院にかかった日が初診日になる場合もあります。
併せて障害年金の申請をする初診日から1年6か月を経過しているか、障害が固定化していることを確認します。
初診日の病院が分かったら、その病院で受診状況等証明書を作成してもらい、初診日の証明として申請書類と一緒に提出します。【※初診日の病院が記載作成】
受診状況等証明書についての詳細はこちら↓↓↓
ブログ![]() ☆解説!受診状況等証明書とは??
☆解説!受診状況等証明書とは??
通常の申請であれば、障害認定日以降3か月以内の診断書が必要です。【※障害認定日時点での病院で主治医が記載作成】
障害年金申請用の診断書は8種類あり、気分(感情)障害の申請には「精神の障害用」の診断書を使用します。
診断書は次の場所で交付してもらうことができます。
・市町村の国保年金課
・全国の年金事務所
・街角の年金相談センター
・日本年金機構のHPからダウンロード →こちらからダウンロードできます
精神疾患用の診断書を記入できるのは精神科の医師か精神保健指定医に限られるため、現在かかっている病院の主治医へ依頼します。
精神の障害用の診断書は日常生活状況を記載する箇所が多く、障害年金の認定に大きく影響する部分です。日常の状況を適切に診断書に反映してもらうため、生活の状況を普段から詳しく伝えておくことが大切です。
最後に病歴・就労状況等申立書を作成します。【※請求者が記入作成】
この申立書は最初に病院にかかったときから現在までの病歴を記載します。一時症状が安定して病院にかかっていない時期があった場合でもその間の状況を記載するなど、現在までの流れを途切れることなく記載する必要があります。
病歴・就労状況等申立書は日本年金機構のHPからダウンロードできます。→こちらから
以上の書類が不備なく揃えて申請し認定がでると、障害年金を受給することができます。